47都道府県の手仕事を、文化を継ぐスニーカーで世界の街角へ。

47WAZA KICKS
47都道府県の手仕事を、文化を継ぐスニーカーで世界の街角へ。
-
47WAZA KICKS リーダー / SERENDO株式会社 代表 藤本彩香(あやか)

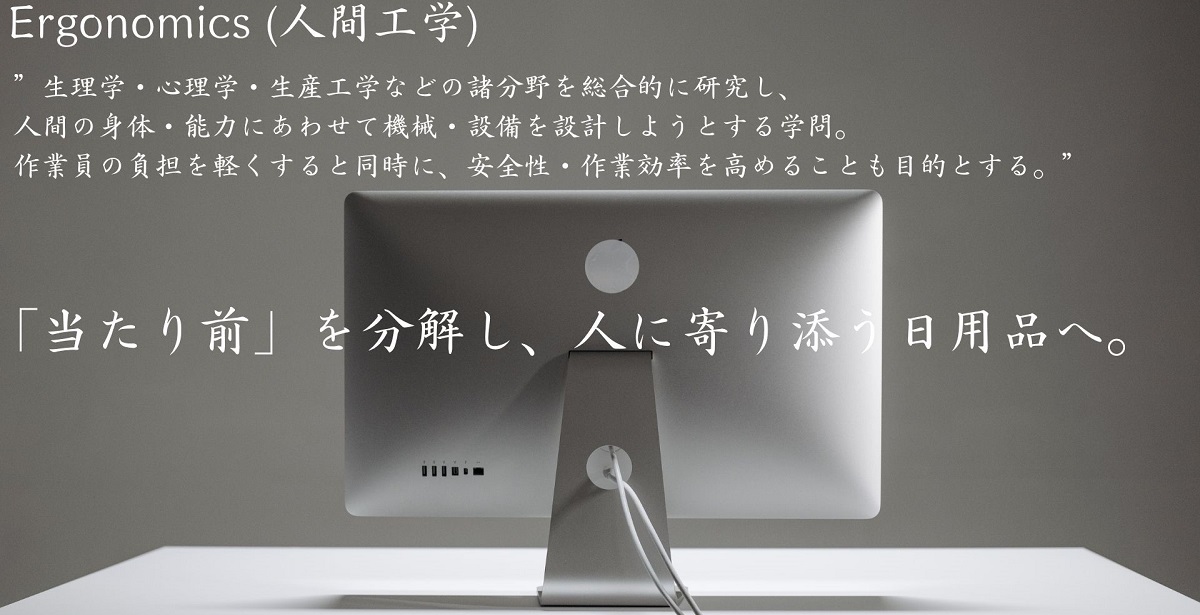
日用品の「当たり前」に問いを立て、モノが人に寄り添う未来へ。



私たちは、日用品に潜む「当たり前の不便さ」を手がかりに、人間工学の視点からデザインを問い直すプロジェクトです。
歴史的慣習や技術的制約によって形が固定化された製品をゼロベースで分解・再定義し、より自然に人に寄り添う形を探ります。私たちはいま、「人がモノに合わせている時代」に生きていると感じています。その構造を問い直し、「モノが人に合わせる」時代へのパラダイムシフトに挑戦します。
傘を差して歩いていたときに、ふと「この傘の形状は人間に最適化されているのだろうか?」と疑問に思いました。雨を最大限に防ぐための持ち方と、人間が楽に傘を持てる持ち方の間にギャップがあることに気づいたのです。この具体的な気づきを抽象化してみたとき、我々が普段使っている製品の形や機能には本質的な理由があるとは限らないどころか、「これまでそうだったから」という惰性的な構造に支配されている場合が少なくないという結論に至りました。こうした問題意識から、本プロジェクトを始動しようと決めました。
日常で使用される多くの道具は、長年の慣習や製造上の制約によって設計が固定化しており、私たちはそうした製品に無意識のうちに適応し、不自然な姿勢や不快な操作感を受け入れて生活しているのが現状です。こうした背景を踏まえ、私たちは「エルゴノミクスに基づいて再設計された製品は、従来品よりも直感的に使いやすく、使用中の身体的負担を軽減できる」という仮説を立てました。
まず、対象となる製品を選定し、使用目的や動作パターン、身体構造などの観点から、必要な機能要件を再定義します。次に、その製品のプロトタイプを実際に制作し、100BANCHの展示スペース等を活用して利用者に体験してもらう実験を行いたいと考えています。このプロセスを通じて、人間工学の視点から素材・構造・形状・操作性を見直し、使用時の動作の自然さや身体への負荷、快適性といった観点で比較・評価を行います。
この3カ月間の目標は、以下の3点です。
①人間工学に基づいたプロダクトのプロトタイプを完成させる
②その使用性と身体負荷の有無を検証する実験を実施する
③ワークショップを通して、共感を呼ぶ形で「プロダクトデザインの再定義」の価値を広げるコミュニケーションの場をつくる
人の生活に深く根ざした道具だからこそ、実際に「使ってもらう」ことで初めて見える課題や可能性があると信じています。100BANCHという開かれた環境でこそできる、実験的かつ実践的な検証を通じて、プロダクトデザインに新たな視点を提示していきたいと考えています。
100年後、道具は「人が使い方を学ぶもの」ではなく、「人の身体や習慣に自然と寄り添い、導いてくれるもの」へと進化していてほしいと考えています。私たちが目指すのは、誰もが自分の身体的特性や環境に合った道具を、誰もが違和感なく使いこなせる社会です。無理な姿勢や不自然な動作を強いられることなく、正しい動きが無意識に導かれる。そんな未来の実現を目指します。

ERGONOMI リーダー守安巧(たくみん)
医学を学びながら、神経科学・意識研究に関心を持ち、「人の内的な経験や感覚を、社会やモノづくりにどう翻訳できるか?」という問いを探究。100BANCHでは、日常の「なんとなく疲れる」「なぜか使いづらい」といった微細な感覚に目を向け、生活道具のプロトタイピングと、感覚を起点にしたワークショップの社会実装に挑戦中。

ERGONOMI 製作班木原悠太
企業が社会的価値と経済的価値をどのようにしたら同時に生み出せるのか、ということを考えてきました。特に気候変動の解決と経済成長の同時達成に興味を持っていました。100BANCHでは、消費者に少しでも役立つものでありつつ、利益を生み出せる身近な商品を実際に製作していきたいです。

ERGONOMI 製作班中村凜
理系の工学部という立場にいる中で、経済学や社会学など文系分野と連携の難しさを感じます。これまで非理系分野も積極的に取り組み、異なる視点を持つことの重要性を学んできました。100BANCHでは、多角的な視点を活かして、人と人、分野と分野をつなぐ「橋渡し役」として、俯瞰的に課題に向き合っていきたいと考えています。